FP・専門家に聞く
2026.02.12
【資産運用】資産形成の鍵は「長期保有」?積立投資と一括投資の投資利益を徹底比較!(横田健一氏)

Share
公開:2025.08.07
更新:2025.10.10

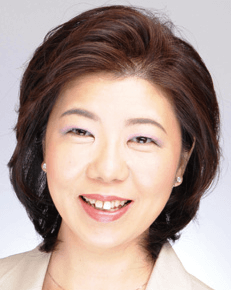
「相続・終活」の第3回目は、「後悔しない葬儀を執り行うには?」について、解説していきます。
厚生労働省によると、2021年の死亡場所の割合は、医療機関が67%、自宅が17%、介護施設・老人ホームが14%となっています。図表1は都内近郊の病院で亡くなり、仏式で葬儀を行った場合の流れです。
死亡が確認されると、故人の搬出が求められるため、葬儀社を探し依頼しなければなりません。遺族は病室の片付けや死亡診断書の受け取り、会計窓口が開いていれば病院への支払いなど、様々なことを短時間でしなければなりません。そのため、この時点で葬儀社をじっくり検討している余裕はほとんどない、と認識しておくとよいでしょう。たいていの人は初めての経験で、何をやっていいか、お葬式にいくらかかるか、どんなお葬式をすればいいのかわからず戸惑います。そのため、親の場合は本人が元気なうちに事前に見積もりを取っておくと、電話一本で進めることができ、スムーズに執り行えます。
見積もりは必ず実際に葬儀社に行って対面で話を聞くことがポイントです。もちろん、お葬式はいつ行うことになるのかわかりませんから、見積もりを取るタイミングは難しいのですが、親自身に行動してもらうのが自然でしょう。ただし親だけで行くのではなく、喪主になると思われる人も一緒に行くことが大切です。実際に出向くと、本人の要望も伝えられ、喪主予定の人もわからないことは聞いておけるうえ、おおよその金額もわかります。
何より実際に葬儀社に出向き話を聞くと、「ここは駅から近くて便利だけど、対応が事務的だな」とか、「小さな葬儀社だけど、ちゃんと遺族の気持ちに寄り添ってくれそうだな」とか、会ってみてわかる印象が必ずあるはずです。
あまり候補を増やすとかえって迷ってしまうので、会館(斎場)を持っている葬儀社と、持っていない葬儀社の2社から見積もりを取ることがお勧めです。「何かあったときにはお願いしたいと思います」と言って、見積もりをもらい、連絡先を聞いておけばいいのです。
葬儀は2つのもので成り立っています。1つは物品。もう1つは人、つまりスタッフ。物品は安くできますが、経験やいろいろなノウハウを身につけているスタッフを見極めることは難しいもの。そのため、対面での見積もりは絶好の機会なのです。
互助会に親が入っている、というケースもあるでしょう。ただ積立金だけで葬儀ができると思っている人が多く、トラブルにもなっているため、必ず積立金以外にどれくらいかかるか確認しておきます。
また、同居の親に内緒で見積もりを取る場合は、郵便物などは送らないで、と言えば送ってきません。
もちろん、葬儀社を選ぶ基準は人それぞれ。価格もその1つです。でも葬儀後に後悔することだけは避けてほしいのです。あらかじめ葬儀社を決めておけば後悔しないというわけではないのですが、急いで決めた葬儀社より、自分の目、家族の目でいいと思った葬儀社のほうが納得できるのは明らかです。
葬儀社選びとともによく検討しておきたいのが、葬儀のスタイルです(図表2)
| 一般葬 | 身内や町内の人、知人など故人と縁のある方に広く訃報を知らせ、故人を見送る葬儀。供花や香典をいただけるため、費用負担が少なく済むことがある。 |
|---|---|
| 家族葬 | 定義がないため、家族のみ、親戚含む、故人の友人含む等、解釈はそれぞれ。故人と縁のある方々の「お別れしたい思い」をくみづらい葬儀でもある。 |
| 一日葬 | 初日の通夜を行わず翌日の葬儀・告別式のみを行うもの。一日で済むため遺族の負担が少なくなるが、費用が大幅に削減できるわけではない。 |
| 直葬 | 葬儀を行わず火葬のみを行うもの。法律で死亡後24時間は火葬できないため、安置が必要。遺体の処分と感じる親族とトラブルになることがある。 |
| 無宗教葬・自由葬 | 宗教にとらわれず自由に行う葬儀。読経を行わない時間の過ごし方の準備が必要。無宗教葬に慣れている葬儀社に依頼するほうが安心。 |
| 市(区)民葬 | 市(区)民葬の提供内容では葬儀の一部しか含まれていないためオプション追加は必須。自宅で少人数設定のため、斎場利用は家族葬より費用が高くなるケースが多い。 |
| お別れの会・偲ぶ会 | 平服で出席しホテルやレストランなどでの軽食、献花等を行うのが一般的。参列より費用が高い、拘束時間が長いため負担と感じる人もいる。 |
出所:明石久美氏作成
コロナ禍の影響もあり、特に都市部では「家族葬」「一日葬」、火葬だけを行う「直葬」も増えています。
しかし、「家族だけでやるので」と済ませたら後で親戚から非難された、友人が、「お焼香をさせてください」と次々と訪れ、その度にお香典返しをして結局費用や手間もかかった、などの声を聞くこともあります。それなら、最初から故人の友人や知人を呼んだほうがよほどすっきりするのでは、と思います。もちろん、亡くなった方の年齢や友人らとの交流関係によります。
お葬式は悲しみを共有する場です。故人にきちんとお別れが言いたい、感謝を伝えたい人もいるので、そこに来てもらうことで一緒に悲しむことができます。家族も心の区切りをつけることができますし、参列者も遺族の悲しむ様子を見て「何かのときには力になってあげよう」とか、「しばらくそっとしてあげよう」、とか受け止めることもできます。そのような場を共有できたほうがお互いによかったりするわけです。
本人の希望も大切ですが、最終的にお葬式を行うのは遺族です。故人の思いを尊重しつつも、遺族が後悔せず、心穏やかに故人を送れる形が望ましいといえるでしょう。送られる側(本人)は自分目線だけではなく、行う人目線でも考えてほしいと思います。
市(区)民葬は、自治体と提携している葬儀社が、定められた協定価格や物品で葬儀が行える制度です。自治体がやっているから安く済みそうという印象がありますが、協定価格や提供される物品に含まれるのは葬儀の一部分だけで、実質的にそれだけでは葬儀ができず、別途オプションとして費用が追加されるケースが大半です。また、自宅で少人数で行うような葬儀が想定されているため、斎場を使う時点で高くなってしまうという点で注意が必要です。市(区)民葬で行うのなら、事前に市(区)民葬を扱っている葬儀社に見積もりをもらい確認しておきましょう。
無宗教葬、自由葬という形式もあります。仏式の場合、読経は30~40分、少なくて20分ほどという場合が多いですが、無宗教葬、自由葬では読経の代わりになるようなものを何か行わなければいけません。写真をスライドで見せたり、ビデオを流したりといった準備は遺族がしなければならないのです。さらに無宗教葬に慣れていない葬儀社が多いので、慣れている葬儀社を事前に探しておく必要があります。
お別れの会や偲ぶ会は、後日、ホテルやレストランなどで行う形式です。本人が「葬儀は家族だけの家族葬で、後でお別れの会をやってほしい」と希望して、そのとおりにしたとしても、出席者から見れば時間が拘束されるうえに、お葬式に呼んでくれたほうが悲しみを共有できた、会費より香典のほうが安かった、と感じる方がいる可能性も考慮しておくとよいでしょう。
葬儀は「小さいほうが安い」というイメージが定着していますが、一般葬のほうが安く済むケースは多くあります。
葬儀で一番お金がかかるのは祭壇です。一般葬の場合、参列できない人は供花を出してくれます。小さな祭壇を選んでも、供花が多ければ見栄えが良くなるため費用が抑えられます。また、家族葬に比べて会葬者からの香典が多くなるため、遺族の金銭的な負担が結果的に少なくなることもあります。
亡くなった人が多くの方と交流をしていたのなら、その方たちに声をかけたほうが、かえって家族の金銭的な負担は少なくなります。最近のトレンドだから、安く済みそうだから、という理由で決めると、周囲の言葉で傷ついたり、後日の弔問対応に追われたり、後悔したりすることもあります。「家族に金銭的な負担をかけたくない」という故人の配慮がかえって遺族の精神的な負担を増やしてしまう可能性もあるのです。
葬儀費用が少し高かったとしても、後ですごくいいお葬式だった、いいお見送りができたからよかった、と思えるほうがよほど家族は満足できるのではないでしょうか。例えば最近は納棺師に入ってもらうケースもあります。費用はかかりますが、故人の最後のお顔がきれいになるばかりでなく、納棺師の作業の間、家族一緒に見送る時間を持つことができ、きちんとお別れできた、という満足感につながります。
このように送る側の目線を大切にして、後悔しないようなお葬式を考えてほしいと思います。
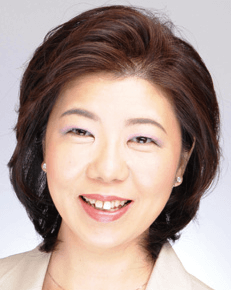
CFP®認定者、明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング 代表
明石 久美 氏
相続・終活コンサルタント、特定行政書士。千葉県松戸市を拠点におひとりさま準備、遺言書や民事信託契約書の作成、相続手続きなど相続業務を18年行っている。講師歴は20年、葬儀や墓などにも詳しく、相続・終活セミナーや研修を全国で行うほか、メディア出演、著書なども多数。
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP・専門家に聞く
2026.02.10
【経済動向】日本経済「失われた30年」は終わったのか?(永濱利廣氏)
FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)
FPトレンドウォッチ
2026.02.12
日々の生活にも大打撃! 急増する「ランサムウェア」での被害
FPトレンドウォッチ
2026.02.09
新生活に向けてチェックしたい 引っ越しに関する手続きリスト(上)
FPトレンドウォッチ
2026.02.04
下取り?買い替え? 不要になったPC・スマホの処分方法
FPトレンドウォッチ
2025.09.03
いったん下がったコメ価格、実りの秋で再高騰?【トレンド+plus】