FP・専門家に聞く
2026.01.27
【家計管理】「家計簿」は必ずしもつけなくていい!?(風呂内亜矢氏)

Share
公開:2025.07.01

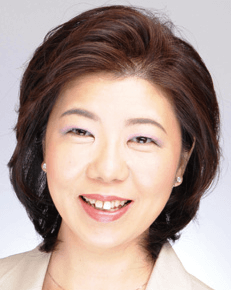
「相続・終活」第1回は、そもそも「相続に必要な情報」とは何なのか、解説していきます。
「終活」という言葉が定着してきました。ところが、自分ではよかれと思って進めた終活も相続発生時には役に立たなかったり、残された家族が困惑するケースがあります。
エンディングノートを書くことが目的になっていて、書いて満足される方も多いですが、専門家から見ればメモであり、法的効力はありません。家族が知っておきたい情報はもとより、相続に必要な情報がきちんと残せているか、伝えられているかも大切です。
では、「相続に必要な情報」とは何でしょうか。
「相続に必要な情報」は、相続発生時に「何が必要になるか」をいわば逆算で考えていくと、はっきりとしてきます。
まず基本となるのが銀行など金融機関の口座(以下、口座といいます)に関する情報です。
口座に関しては、相続発生後、財産の把握をするために、どの金融機関と取引しているのか、通帳がどこにあるのか、何が引き落とされているのか、これらをわかるようにしておくことが必要です。
相続人が知らない預貯金は各銀行へ照会しなければならず、時間がかかります。存在に気がつかない場合、預貯金の解約ができず遺産を手にすることができません。
注意が必要なのは、終活で口座を整理して1つにしてしまうことです。例えば、通帳の名義人が認知症だと金融機関が知り、その1つしかない口座が凍結されるなどの緊急事態が起こった時に困る場合があります。せめて2、3の口座は残しておくとよいでしょう。さらに配偶者や子など口座の管理を任せたい人がいる場合は、“代理人カード”を作成しておくと、そのキャッシュカードで入出金管理ができるうえ、カード紛失や磁気破損の際にも困らずに済みます。
預貯金の残高は、家族に伝えなくても大丈夫です。取引している金融機関をわかるようにしておく目的は、財産の把握の際に困らないようにするためです。あくまでも口座があること、通帳の保管場所の情報に留め、残高は伝えないほうが賢明です。
次に欠かせないのは口座引き落としに関する情報です。金融機関は口座名義人の死亡を知らなければ口座を凍結しません。そのため、「亡くなった本人の銀行口座は、しばらくそのままにしておき、年金などの入金やクレジットなどの引き落としが落ち着いた頃に口座を凍結したい」と希望する遺族が多く見られます。しかし、不要になった各種サービス利用料金等が引き落とされてしまう恐れがあり、無駄に相続財産を減らすことにつながるため、どこから引き落としがあるかを生前に情報として伝えておくほうが合理的です。
ここからは、どのようにして相続財産を把握していくか、「相続に必要な情報」を具体的に確認していきましょう。
株や投資信託といった有価証券は、郵送されてくる取引残高報告書などや残高証明書を取得して概算額を把握します。取引している証券会社がわからない場合、証券保管振替機構(略称:ほふり)の登録済加入者情報の開示請求をします。手数料は1件あたり6,050円(税込)です。ただしすべての証券会社などがわかるとは限らないため、注意が必要です。
保険の場合は、保険証券や提案書などで保険金額や受取人を確認します。加入している保険がわからない場合は、生命保険契約照会制度で確認することができます(3,000円(税込)の手数料がかかります)。ただし、損害保険、共済、団体信用生命保険、少額短期保険、海外保険などは対象外になるため、個別に問い合わせをする必要があります。
また、金融機関によっては照会に2カ月ぐらいかかる場合もあり、財産目録を作るまでに時間がかかってしまい、相続放棄の判断までの時間が迫ってしまったり、相続税申告の期限に間に合わない可能性もあります。
不動産は固定資産税の納税通知書にある課税明細書で概算評価額をつかみます。わからない場合は、固定資産評価証明書や名寄帳などを取得します。また法務局で土地と建物の不動産登記事項証明書を取得し、所有者や持分、抵当権などの有無を調べます。
動産に関しては、乗用車、オートバイ、貴金属、ゴルフ会員権、骨董品など価値のある物の価額を確認します。
さらに未払金や借金の状況もまとめます。公共料金、電話代、クレジットカード、市県民税や固定資産税、定期購入、サブスクリプション、各種ローンなどを調べます。
未収入金も確認します。例えば賃貸不動産の家賃や送電線、電柱などの収入がある場合はその内容を調べます。その他、未支給の年金などは通知書や契約書などで確認します。
これらの細かい確認はかなり時間と手間がかかるため、遺族には負担になりやすいです。だからこそ、役所からの通知書や毎月払っているものの通知書、保険証券、契約書など、これらの保管場所をわかるようにしておくことが大切です。
エンディングノートは「何のために情報を残すのかをよく考えること」が重要です。
エンディングノートは、家族が知っておくべき様々な情報を伝える手段として有効なツールです。ただし、財産の詳細や誰にどれだけ分けるか、といった相続の情報は残さないことにも注意が必要です。法的効力がないため、エンディングノートだけで終活が完結しないことをよく理解したうえで、ノートの保管先を伝え、定期的な見直しを心掛けましょう。
医療や介護を受ける際に役立つのが、既往症、アレルギー、服薬、かかりつけ医などの情報です。告知や延命治療の要望はその理由も伝えておきます。理由を知ることで、いざというとき、家族が判断する助けになります。これらの情報は緊急連絡先とともに玄関先などすぐわかる場所に置いておいたり、保険証(マイナ保険証)と一緒に携帯しておきましょう。
「好きな〇〇、苦手な〇〇」など、嗜好についても、生活上では伝えておきたい情報の1つです。情報があれば意思疎通が難しくなった場合でも、望んだ生活に近づけます。飲食の好みや味付け、色、香り、本、音楽、場所、言葉などがこれにあたります。
菩提寺の連絡先、宗派、訃報の連絡先は相続発生後、すぐに必要になるため、わかるようにしておきたい情報です。遺影用写真の保管場所の情報も同様です。
現在墓を持っている、あるいは継いでいる場合は、墓地管理者の連絡先や規約の保管場所、お布施の額、石材店の連絡先などを残しておくと、次の承継者が困りません。
レンタル倉庫やレンタル菜園など外部サービスの契約、預かり品や借り物などの返却先、郵便受けや宅配ボックスの開け方なども伝えておきたい情報です。
パソコンやスマートフォン(以下、スマホ)で取引しているものは、デジタル遺品(遺産)になります。必ず必要なのはパソコンやスマホのログイン方法、ロック解除方法です。次に、デジタルのため、情報がわからないと予想されるもの、自分しか知り得ない情報は、必ず後で家族がわかるようにしておくことも大切です。サブスクや定期購入先、Web明細、携帯電話代と合算払いしているものなどが該当します。
ただし、セキュリティ上、パスワードを書いておくのは避けておくとよいでしょう。データ名と保存先、インターネットのURL、アカウントやID、パスワードのヒント、利用目的や、行ってほしいことなどをわかるようにしておくのがポイント。パスワードは別の紙に書き、照合すればわかるようにして、保管場所を家族などに伝えておきます。
自分の「思い」「要望」より、「必要な情報は何か」、「なぜその情報を残さなければならないか」を考えて準備することが大切です。改めてご自身の終活を、この視点から見直してみてはどうでしょうか。
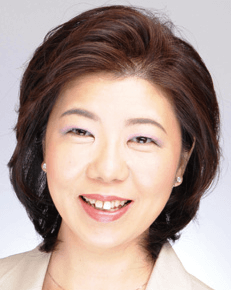
CFP®認定者、明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング 代表
明石 久美 氏
相続・終活コンサルタント、特定行政書士。おひとりさま準備、遺言書や民事信託契約書の作成、相続手続きなど相続業務を18年行っている。講師歴は20年、葬儀や墓などにも詳しく、相続・終活セミナーや研修を全国で行うほか、メディア出演、著書なども多数。
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP・専門家に聞く
2026.01.20
【社会保障】公的年金とiDeCoで最強の自分年金を作る(井戸美枝氏)
FPトレンドウォッチ
2026.01.26
「AIで稼ぐ」とは? 知っておきたいAIの最新事情(上)
FPトレンドウォッチ
2026.01.27
「AIで稼ぐ」とは? 知っておきたいAIの最新事情(下)
FPトレンドウォッチ
2026.01.22
眠っていた「タンス預金」、そのリスクと遺品整理での対処法
FPトレンドウォッチ
2026.01.23
自動車保険料が高騰する背景と、賢い見直しポイント
FPトレンドウォッチ
2026.01.19
年金生活の家計収支はどのくらい赤字になる?【トレンド+plus】