FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)

Share
公開:2025.07.10
更新:2025.10.10

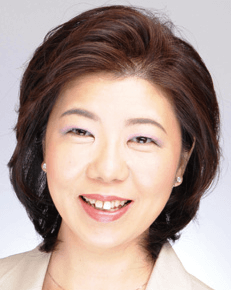
「相続・終活」の第2回目は、確実に執行するための遺言書のポイントについて、解説していきます。
遺言書の作成は「終活」の要ともいえる部分。その必要性は多くの人が感じているのではないでしょうか。
主に利用される遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。最近は法務局による自筆証書遺言の保管制度もでき、自分で作成したいと考えている方も増えているかもしれません。自分で遺言書を書くこと自体、難しくはありませんが、自筆証書遺言は文字通り「自筆」、つまり手書きです(財産目録はパソコンでの作成や通帳コピー添付でも可)。自筆証書遺言のデメリットをきちんと理解したうえで、なぜ専門家の立場からは公正証書遺言を勧めるのかも含めて考えてみましょう。
例えば「自宅を妻に相続させる」。「自宅」だけでは、どこの不動産なのか、土地なのか建物なのか、わかりません。最低限「自宅」の土地、建物が特定できる情報を書くことが必要です。なぜなら不動産が特定できないと、名義変更できない可能性があるからです。
相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」という書き方が基本ですが、もしも相続人に「遺贈させる」と書くと、場合によっては遺贈扱いになり、不動産がある場合は登録免許税が高くなる可能性があります。また、修正の方法にもルールがあり、間違えるとその部分だけ無効扱いになってしまったり、遺言執行者が書かれていない場合は、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらったりする必要が出てきます。
夫婦はどちらが先に亡くなるかわかりません。遺言者の夫が全財産を妻へという内容を書いていても、夫より先に妻が亡くなった場合、妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます。妻が先に亡くなった場合は「長男に」と書いてあれば(予備的遺言と言います)、長男に渡せますが、この記載がなければ、宙に浮いた財産は遺産分割協議の対象になります。つまり、遺言書で執行できる財産と、残念ながら遺言書では執行できず遺産分割協議になる財産とに分かれることになります。これでは中途半端で、遺言書を書いたことでかえってもめる原因になります。だからこそ、最後まで遺言の内容どおりに実行できるよう、遺言書はあらゆる可能性を考えた予備的遺言を含めて作成することが大切なのです。
2020年から自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。法務局が原本と画像データを保管するため紛失や改ざんが防げるほか、遺言者が亡くなったら、指定された人に遺言書が保管されている旨の通知も送られます。申請手数料も3,900円と安価です。遺言者の死後、家庭裁判所の検認が不要なのも特徴です。
ただし、気をつけなければならない点がいくつかあります。まず遺言者本人が必ず法務局に出向き、顔写真付きの本人確認書類を提示しなければなりません。また、用紙のサイズや余白などのルールが細かく決められているため、その点をクリアしなければ受け付けてもらえません。
そしてなによりも相続発生後、遺言書を「簡単に取り出せない場合がある」という点に注意が必要です。
相続が発生すると、法務局から遺言者が指定した人に「指定者通知」が通知されます。通知を受けた人は「遺言書情報証明書」(=遺言書の画像データ)の請求や遺言書の閲覧ができます。その手続きには「法定相続情報一覧図」または遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票の写しが必要になります。
実は戸籍謄本は「上下(=親子)」は簡単に取れますが、「横(=兄弟姉妹)」は簡単ではないのです。
例えば、父が亡くなり相続人が母と3人の子どもという場合、相続人は被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を、広域交付制度を利用してどの自治体でも入手することができます。
ところが、相続人が妻と亡夫の兄と姉という場合、相続人を確定させるためには、亡夫と、亡夫の父と母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要になります。妻は亡夫の出生時からの戸籍謄本等は広域交付制度を利用して取得できますが、亡夫の父母の戸籍謄本等の取得は広域交付制度の対象外になるため使えません。父の本籍地が生まれてから死亡するまで、A、B、Cと動いていたら、死亡時の本籍地C市役所から出生時の本籍地A市役所と遡って入手する必要があります。母の場合も同様です。いわゆる異父・異母兄弟姉妹がいるかどうかを調べなければならないからです。ケースによっては、戸籍謄本等の取得がスムーズにできず、専門家に依頼することもあります。
また、相続人の兄弟姉妹が確定しても再婚相手の子どもで、交流もなく居場所も不明、という場合もあります。
このように大変なら法務局に預けず自宅に遺言書を保管しておけばいいのでは、と考えるかもしれません。その場合は遺言者が亡くなったあと家庭裁判所の検認が必要になりますが、その際にも同じ戸籍謄本等が必要になります。
だとしたら、元気なうちに専門家に依頼してすべての書類を整えてもらい、予備的遺言も含めた内容にして公正証書で作成したほうが相続人は困らないのではないでしょうか。
ちなみに、法務局で交付してもらう「法定相続情報一覧図」は、預貯金の解約や相続登記、相続税の申告など、相続手続きで戸籍謄本等の代わりに利用できる公的証明書ですが、交付してもらうにはやはり相続人を確定させる戸籍謄本等が必要になります。
遺言書を作成しておきたいケースはいくつかあります。まず誰も相続人がいない人、そして子どもも両親も祖父母もおらず、兄弟姉妹が相続人になる人です。特に配偶者と兄弟姉妹間が相続人の場合、遺産分割協議は大変になりがち。兄弟姉妹には遺留分(最低限相続できる割合)がないため、配偶者に相続させたい財産を決めておく遺言書を作成しておくと全財産を配偶者に相続させることができ、配偶者は困らずに済みます。
また、前の配偶者との間の子どもが相続人の場合やそもそも交流がない、行方がわからない相続人がいる場合も同様です。行方不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人をつけてもらい、遺産分割を行う必要があるからです。さらに、判断力のない相続人がいる場合も、後見人等が遺産分割を行う必要が出てきます。後見人がついていない場合は家庭裁判所に選んでもらい、その後見人に遺産分割とその後の財産管理を行ってもらうことになります。このようなケースの場合は特に、遺言書の作成をお勧めします。
よく「遺産分割協議では法定相続分で分けないといけない」と誤解していて、「法定相続分で分けたくないから、遺言書を作る」と言う人がいます。「遺産分割協議は自由な割合で決められますよ」と言うと驚かれますが、家族仲が良く、話し合いでまとまるなら、遺産分割協議で自由に遺産を分けても問題ないのです。
専門家から見ると、ポイントはそこではありません。家族仲が良くても、遺産分割がスムーズに進まないケースや相続手続きが大変になるケースでは、遺言書はあった方がいいですし、なるべく早く作ったほうがいい、という結論になるのです。
公正証書遺言ではどれくらいの費用がかかるのか、気になると思います。
シンプルな内容の場合、直接公証役場へ行き、作成してもいいでしょう。公証役場の手数料は全国一律ですが、誰がどのくらいの額の財産を相続等するのかで受け取る価額に応じた手数料が1人分ずつ加算されていくため、遺言書に登場する人数が多ければより高くなります。地域によりますが、4万円台から10万円ほどが目安です。
公証人は「対策」までは行わないため、複雑なケースでは、作成のサポートを弁護士や行政書士といった専門家に依頼するほうが無難です。
その際の費用は様々ですが、「生きているときにお金を使って家族が困らないようにしておくのか、亡くなったあとに相続人にお金や時間の負担をしてもらうのか」の違いだと考えてみてはどうでしょうか。
自分には遺言書が必要か、作成は自筆証書遺言、公正証書遺言どちらがいいのか。財産の多寡ではなく、残された家族の状況をもう一度考えて、検討してみてはいかがでしょうか。
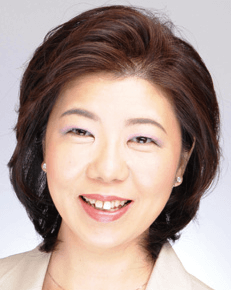
CFP®認定者、明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング 代表
明石 久美 氏
相続・終活コンサルタント、特定行政書士。千葉県松戸市を拠点におひとりさま準備、遺言書や民事信託契約書の作成、相続手続きなど相続業務を18年行っている。講師歴は20年、葬儀や墓などにも詳しく、相続・終活セミナーや研修を全国で行うほか、メディア出演、著書なども多数。
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP相談事例
2026.01.28
40代専業主婦。自営、無保険の夫が急死。長女を進学させられる?
FPトレンドウォッチ
2026.01.29
【速報版】2026年度税制改正大綱のポイントを解説!(上)
FP・専門家に聞く
2026.01.29
【税制改正】改正で注意したい2025年分の確定申告(備 順子氏)
FP・専門家に聞く
2026.02.02
分野/FP・エコノミストの一覧はこちらから!
FPトレンドウォッチ
2026.02.03
指数上昇で注目集まる J-REIT市場
FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)