FP・専門家に聞く
2026.02.12
【資産運用】資産形成の鍵は「長期保有」?積立投資と一括投資の投資利益を徹底比較!(横田健一氏)

Share
公開:2025.11.06
更新:2025.11.28
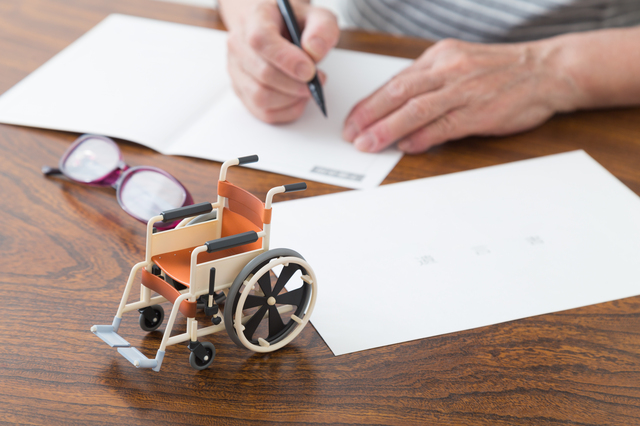
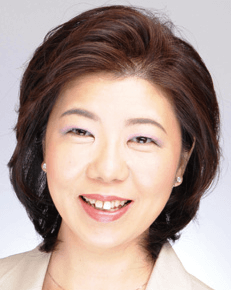
「相続・終活」の最終回は、「後悔しないおひとりさまの生活サポート&相続の準備」について、解説していきます。
これまで、相続や終活について一通り押さえてきましたが、最後に「おひとりさま」の生活サポートと相続の準備について取り上げたいと思います。おひとりさまに該当する場合に、準備や対策をしておくとよい4つの契約書+遺言書(以下、「5つの契約書など」とします)があります。ポイントを押さえ、準備しましょう。
| 時期による分類 | 契約等の種類 | 目的 | 契約開始後の報酬の目安※ |
|---|---|---|---|
| 生前のための準備 | ①見守り契約 | 定期的な連絡や面談によって健康状態や生活状況、判断能力の低下などの確認をしたりする | 月額5,000円〜 |
| ②財産管理等委任契約 | 判断能力があっても体が不自由になってしまった時などの財産管理や見守りをする | 月額3万円〜 | |
| ③任意後見契約 | 判断能力が低下した時に財産管理や身上監護をする | 月額3万円〜 | |
| 死後のための準備 | ④死後事務委任契約 | 葬儀、納骨、遺品整理など、死後の様々な手続きをする | 30万円〜 |
| ⑤遺言書 | 遺産をどうするかの指定をし、遺言執行者に遺言どおりの手続きをしてもらう | 30万円〜 |
※契約書など作成時の専門家への報酬、公証役場の手数料は別途必要
5つの契約書などのうち、生前の生活サポートのために準備しておきたいのが、①見守り契約、②財産管理等委任契約、③任意後見契約です。一方で死後のために備えておきたいのが、④死後事務委任契約、⑤遺言書です。
「おひとりさま」にもいろいろなタイプがあり、備えておきたい契約も異なります。ケース別に見ていきましょう。
甥や姪に支援をお願いしたい場合は、事前に意思確認が必要です。しかし、もともと甥や姪との付き合いがなければ支援を望むのは難しいかもしれません。 甥や姪が支援をしてくれるとしても、本人の代理で手続きなどを行うときには、相手方から本人の委任状を求められることがあります。しかし本人が委任状を作成できない状態にあったら困ってしまいます。そのようなときに備えて「②財産管理等委任契約」、「③任意後見契約」を、支援してもらう甥や姪と結んでおくと安心です。さらに、甥や姪に死後のことまで依頼をするのなら、甥や姪が相続人か否かに関わらず、「⑤遺言書」を作成し、生前の費用の精算や死後にかかる費用の支払いなどができるようにしておきましょう。
頼れる親族がまったくいない場合は、先に挙げた5つの契約書などの準備をしておきましょう。費用面が不安な場合は、生前のことは行政や福祉のサービスを活用しつつ、最低限「④死後事務委任契約」と「⑤遺言書」だけは準備したいところです。
夫も妻も頼れる親族がいるならよいのですが、いない場合には、夫婦ともに「①見守り契約」「②財産管理等委任契約」「③任意後見契約」「④死後事務委任契約」「⑤遺言書」を専門家に依頼しておくと安心です。また、夫、妻のどちらかが先に亡くなった場合に財産を誰に渡したいのか、夫婦ともに亡くなったときには夫婦2人の財産をどこに渡したいのか、夫婦で考えておく必要もあります。
5つの契約書などの中でも「①見守り契約」と「②財産管理等委任契約」は契約したからといってすぐにスタートするわけではなく、依頼したいときからスタートさせることができます。「③任意後見契約」は、判断力が低下しなければ利用することはありません。つまり、契約が開始されなければ、使わずに済むものなのです。いざというときには使えて、必要でなければ使わずに済む、おひとりさまにとっての「お守り」のようなものと思えばよいでしょう。
なお、「死後事務委任契約」は本人の死後、すぐに必要な支払いに備えて、依頼先(受任者)に預託金(数十万円〜)を預けておくケースがほとんどです。
頼れる親族が近くにいない場合、「死後事務委任契約」で困るのは死亡届の届出人欄への記入です。届出人欄に記入できる人は、親族、家主、地主、管理人など法律で決められているため、死後事務委任契約の受任者では記入ができません。しかし、任意後見契約があれば、契約を受任した人が記入できるため、すぐに死亡届の記入欄に記入できる人がいない場合は、「④死後事務委任契約」と「⑤遺言書」に加え、「③任意後見契約」も検討すべきです。死亡届の提出が遅れれば、火葬の許可がもらえず葬儀まで時間がかかってしまう可能性があるからです。
もう1つ注意したいのが、「とりあえず遺言書だけでも作っておこう」と取り組むことです。おひとりさまの場合は、前述のように死後事務のこともあり、5つの契約書などを軸に終活を考えることが基本ですが、その全体像を決めないまま、例えば「⑤遺言書」を急いで作成してしまうと後悔することがあります。
たとえば、遺言執行者(遺言書どおりに手続きする人)が専門家のA氏、という公正証書遺言を作成したものの、A氏が死後事務委任契約を受任していないとします。その場合、死後事務委任契約のみを受任してくれる別の人を探さなければなりません。しかし、死後事務委任契約のみの受任をしていない専門家や団体もあったり、受任してくれるにしても200万~300万円といった預託金が必要だったりします。死後事務委任契約の受任者が遺言執行者へ費用の支払いや精算を求めても、直接相続人へ請求するように言われてしまう可能性が高いため、報酬を含めた額を預かっておきたい事情があるからです。
ある1人の専門家に依頼して全体の対策を決め、その結果、遺言書を先に作っておこう、ということなら問題ありません。ただ、「とにかく遺言書だけ」ということは避けてください。おひとりさまの場合、第2回「確実に執行するための遺言書のポイント」でも取り上げたとおり、確実に遺言執行ができるような遺言書にしておかなければならないため、甥や姪に支援をお願いするにしても、相続業務を行っている専門家の力を借りたうえで作成するようにしたほうが安心です。
相続業務を行っている専門家に依頼すると、包括的にその人に必要な契約、内容は何かを考えてくれて、一緒にプランニングができます。また、相続に強い専門家同士のネットワークがあり、必要に応じて税理士など、紹介してもらえるのも心強い点です。そうしたネットワークは最新情報にも詳しい人ばかりですから、信頼性は高いといえます。
専門家に依頼するデメリットはやはり費用面です。先の5つの契約書などを専門家に依頼すると、セットで15万〜50万円、それ以上かかる場合もあります。さらにこれらは公正証書にするため、公証役場の手数料が8万〜17万円程度、場合によってはそれ以上かかります。
契約書などの事前準備をするだけでも費用がかかるうえ、実行援助をしてもらう際にも費用がかかるわけですから(図参照)、躊躇するのも当然です。しかし、費用を支払ってでも、自分の今後のために、周囲に迷惑をかけないために、準備しておきたい契約があるなら早めに着手したほうが安心です。
専門家を選ぶ際のポイントは、費用はもちろんのこと、相性や経験、それに年齢差も考慮することです。自分の預貯金の管理や将来のことを託すわけですから、やはり相性は大切です。実際に会ってみれば、話しやすいか、自分と合うかどうかわかります。年齢差は見落としがちですが、理想は20歳ぐらい離れていること。また専門家にもしものことがあった場合、引き継いでくれる人がいるかも必ず確認しましょう。
これまでこのシリーズで紹介した様々な終活、対策は、今後生活するうえで、自分自身や家族が困らないために備えておくものです。準備はできるときにしておかなければ難しくなります。健康維持、楽しく過ごせる仲間や居場所、趣味など人生を豊かに彩るものも大切にしつつ、今後の人生をどのように過ごしていきたいのか、立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。
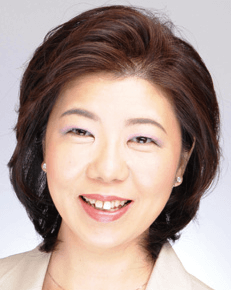
CFP®認定者、明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング 代表
明石 久美 氏
相続・終活コンサルタント、特定行政書士。千葉県松戸市を拠点におひとりさま準備、遺言書や民事信託契約書の作成、相続手続きなど相続業務を18年行っている。講師歴は20年、葬儀や墓などにも詳しく、相続・終活セミナーや研修を全国で行うほか、メディア出演、著書なども多数。
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP・専門家に聞く
2026.02.10
【経済動向】日本経済「失われた30年」は終わったのか?(永濱利廣氏)
FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)
FPトレンドウォッチ
2026.02.12
日々の生活にも大打撃! 急増する「ランサムウェア」での被害
FPトレンドウォッチ
2026.02.09
新生活に向けてチェックしたい 引っ越しに関する手続きリスト(上)
FPトレンドウォッチ
2026.02.04
下取り?買い替え? 不要になったPC・スマホの処分方法
FPトレンドウォッチ
2025.09.03
いったん下がったコメ価格、実りの秋で再高騰?【トレンド+plus】