FP・専門家に聞く
2026.01.20
【社会保障】公的年金とiDeCoで最強の自分年金を作る(井戸美枝氏)

Share
公開:2025.10.02
更新:2025.10.10

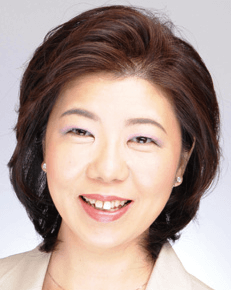
「相続・終活」の第5回目は、「知っておきたい遺品の整理とグリーフのこと」について、解説していきます。
相続発生後、残された家族が直面するのが「遺品整理」です。また残された家族の負担を減らしたいと考え、「生前整理」に取り組む人もいるでしょう。生前整理をして不要なものを整理しておくと、部屋が片付き、室内での転倒予防にもなるというメリットもあります。
気力と体力と時間があれば、自分で行うのがもっとも費用を抑えられますが、難しいときは業者の手を借りるのが現実的です。
まずは亡くなった後に行う「遺品整理」の場合。遺品整理業者によって大事なものを捨てられてしまった、料金が見積もりより高くついたなど、いろいろなトラブルも聞き及ぶため、業者選びは慎重にしたいもの。そこでまず確認したいのがその業者の母体(もともとの本業)です。例えば不用品回収業者、産廃処理業者なら、ごみ収集だけするのが一般的です。リサイクルショップや便利屋が母体の場合、業務の一環として遺品整理も行うという位置づけです。
これに対し、遺品整理専門の業者も存在します。専門の遺品整理業者は何日かかけて封筒の中も全部1つずつ開けて、いるものなのか、いらないものなのか仕分けていきます。1つずつ確認しないで必要な書類を捨ててしまうと、後で相続手続きをするときに困るからです。一方、リサイクルショップは買い取り可能なものは持っていってくれますが、仕分けまではしてくれない場合が多いようです。
遺品整理業者を選ぶにはどうすればいいのでしょうか。まずは現場まで来てもらうことが大事です。一般的にインターネットでできる簡易的な見積もりは2LDKいくら、3LDKだといくら、といった目安であって、実際に来てもらって細かい確認をしないと見積額はわかりません。
業者は部屋ごとにチェックしながら、遺品が全部でどれくらいの量かを判断、トラック何台分になりそうなのかで見積額を出します。駐車スペースや集合住宅ならエレベーターの有無、現場周辺の環境によっても金額が変わってきます。
その際、何日ぐらいかかるか、立ち会いが必要か、一緒に整理ができるのか、買い取りは可能か、最後は簡易な掃除までしてくれるのか、他に追加料金が必要になる場合はあるかなど、気になる点を直接確認しましょう。
見積もりは多くて2社程度がおすすめです。あまり多くの業者に頼みすぎるとかえって迷ってしまうからです。その際、主に何をしてもらいたいかをはっきりさせておくことが重要です。要らないものを不用品として捨てたいのか、買い取りも含めた整理をしたいのか、何を中心にしたいかで選ぶ業者も変わってきます。例えば、父親が亡くなり母親だけになった家に業者が入るのは防犯上心配な場合。遺品が少ないのなら、不用品だけ持って行ってくれる不用品回収業者にお願いするのがいいかもしれません。遺品が多く、その後空き家になるのだったら、本格的に業者に入ってもらって整理するのがいいかもしれません。
こうして見積もりをもらい、依頼することを決めたら、必ず契約書を交わします。
遺品整理の業者は、相続の手続きで必要になる書類を全部把握しているわけではありません。大事なものを捨てられてしまう可能性があるため、自分たちである程度、大事なものだけ分けておきます。そのため、本人が元気なうちに大事な書類の情報はすぐわかるようにしておいたり、保管場所を決めておいたりしてもらうと家族は困らずにすみます。
一方、「生前整理」を業者に依頼する場合も、選び方は同じ。遺品整理同様、何を中心にしたいのかで探してみましょう。遺品整理業者の中には生前整理にも対応するところもあります。
グリーフという言葉をご存知ですか? グリーフとは、「喪失悲嘆」のことです。大切な人が亡くなった後、グリーフの状態になる時期やその影響の度合いは人によって違います。葬儀の時は忙殺されて実感がなくても、徐々に大切な人がいない現実を認識し、もういない、会えないという事実が押し寄せてきます。そうなると、身体と心(感情や思考)、行動に影響が出てきます。人それぞれいろいろな現れ方がありますが、怒りの感情が抑えられず攻撃的になったり、急に泣き出したりと、とにかく普段とは違う感情の動き、状態になります。無気力になる方もいれば過活動になる方もいます。
遺品を見るのも辛くなり、全部捨ててしまう方もいます。しかし2年、3年とたつと、捨てなければよかった、と後悔することも。要するに、グリーフでつらいときとそうではないときでは考え方、捉え方が違うのです。
大切な人を亡くしたときには、グリーフの状態になることとその影響を理解しておく必要があります。グリーフを悪化させないためにも、周囲も含め、グリーフを知ることはとても重要なのです。ちなみにペットロスでもグリーフにつながることも知っておきましょう。
グリーフが悪化するかどうかは葬儀から始まる供養のプロセスによっても違ってきます。例えばお葬式や火葬は、亡くなったという事実を目で見て、現実であると受け止めることでもあります。参列者と悲しみを共有する場があれば、参列者が遺族に対して配慮ない行動や言葉を発することもありません。一方で、本人の希望通り散骨したけれど拝む対象物がないことで、余計にグリーフが加速してしまうこともあります。
グリーフを受容する期間にも個人差があります。例えば配偶者や親が亡くなったケースなら2年程度、子どもを亡くした場合は5年程度、自死や突然死の場合は、より多くの年数がかかるといわれています。大切な人が亡くなってから6カ月くらいまでは一気に状態が低下しますが、その後、徐々に受容できるようになってきます。しかし、一周忌、三回忌といった節目が来ると、また気持ちが落ち込む。それを繰り返しながら、2年、3年、4年、5年と少しずつ回復していきます。
重要なのは、心身や行動に影響がでている状態で相続手続きを行わなければならない点です。接点を持つ機会のある専門家や金融機関などの担当者にグリーフの知識がないと、余計な言葉を発して傷つけてしまうかもしれません。思考が低下していて何回説明を聞いても全然頭に入らない方もいます。
相続手続きには難しい言葉が多く出てきますが、グリーフになるとさらに理解が難しいので、私はより丁寧な対応を心がけています。その時に必要なことを紙に書いてお渡ししますが、わかりやすいように字は大きくして、行間を空けています。「ここは大事です。わからなくなったらこの紙を見てください。もしくは電話をください」と、念を押してお渡しします。他にも大事なことを決める時はほかの人と来てもらうなど、配慮しています。
相談や依頼の際に号泣される人もいます。そういうときは傾聴に徹して、こちらから余計なことは言いません。様子を見て落ち着いたら「ちょっとだけ先にお話を進めてもいいですか」と本題の話をさせていただいています。
また故人の方をなるべく下のお名前でお呼びしています。「故人様」は遺族からしてみると「亡くなった人」と突きつけられていると感じることもあるからです。他にも例えば通帳を預かるときも遺族にとっては遺品と同じなので、ぞんざいに扱わないようにしています。両手で受け取り、内容を見るときは「拝見してもよろしいですか」と確認をしています。
このように、グリーフになっている方は、通常の精神状態にないからこそ、配慮しながら進めていくことを大切にしています。
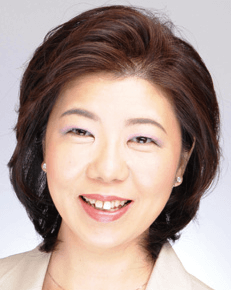
CFP®認定者、明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング 代表
明石 久美 氏
相続・終活コンサルタント、特定行政書士。千葉県松戸市を拠点におひとりさま準備、遺言書や民事信託契約書の作成、相続手続きなど相続業務を18年行っている。講師歴は20年、葬儀や墓などにも詳しく、相続・終活セミナーや研修を全国で行うほか、メディア出演、著書なども多数。
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP・専門家に聞く
2026.01.08
【独立・起業】まずは「自分」を知ることから始めよう(中野克彦氏)
FPトレンドウォッチ
2026.01.14
新成人は要注意! 若年層が巻き込まれやすいお金のトラブル事例(下)
FPトレンドウォッチ
2026.01.15
各地で相次ぐ水道料金の値上げ、今後はどうなる?
FPトレンドウォッチ
2026.01.09
円での資産運用でインフレ対策はできるのか?【トレンド+plus】
FP・専門家に聞く
2026.01.15
【資産運用】「全世界株式インデックスファンド」がシンプルで手間のかからない資産形成に最適な理由(横田健一氏)
FPトレンドウォッチ
2026.01.19
金利上昇で注目を集める「個人向け国債」の魅力に迫る(下)
FPトレンドウォッチ
2026.01.19
年金生活の家計収支はどのくらい赤字になる?【トレンド+plus】
FPトレンドウォッチ
2026.01.20
今後どうなる? 金利上昇局面での住宅ローン事情