FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)

Share
公開:2025.09.04
更新:2025.10.23

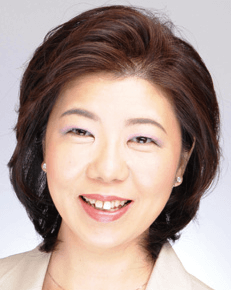
「相続・終活」の第4回目は、「後悔しないお墓選び」について、解説していきます。
「遺骨はどこかに撒いてくれればいい」と、軽く考えている人もいますが、葬儀と同じように、お墓や供養の方法は、ご自身と残される家族のために、しっかりと考えておきたい大切な事柄です。
お墓についてまず押さえておきたいポイントとして、お墓や仏壇・仏具はいわゆる「祭祀財産(さいしざいさん)」に当たり、預貯金などの相続財産ではないという点です。そのため、祭祀承継者(=お墓など祭祀財産を継ぐ人)は相続人でなくてもよいのです。つまり、相続人ではない親族でも祭祀承継者になれるのです。ただし、祭祀承継者は原則1人だけとされています。生前の口頭での指名や遺言書による指定、あるいは地域の慣習によって決まりますが、特に指定がなく、話し合いでも決まらない場合は家庭裁判所での調停や審判によって決定されます。
祭祀を承継し、現在管理している人(=祭祀主宰者という)は、そのお墓に誰を入れるか入れないかを決めることができます。よく「同じお墓に入れますか」という質問を受けますが、墓地の規約の範囲内で祭祀主宰者が認めれば入れる、ということになります。
現在入るお墓がない人は、「すでにある親族のお墓に入る」か、「新しいお墓を購入する」かが主な選択肢となるでしょう。
生前にお墓を購入する人もいますが、そのメリット、デメリットを知っておきましょう。メリットはご自身が望むお墓を選べること、そして自分の財産で購入できることです。もし、お墓がなく、お墓購入などでかかる費用を遺産から支払うよう指定がない場合は誰がどのようにその費用を負担するのか、相続人同士で決めることになります。
一方、デメリットは一度購入すると返還や転売が難しいこと、自然災害などで破損、倒壊する恐れもある点です。場合によっては、購入後すぐに維持費がかかることもあります。
例えば、ご夫婦で入るためにお墓を契約した場合を考えてみます。その墓地の契約が「納骨時から7年間の永代供養」で、先に夫が亡くなり納骨したとします。その後、7年が経過し、妻が8年目に亡くなった場合、永代供養の期間が終了しているため、そのお墓に入れないという事態も起こり得ます。そうならないようにするためには、確実に妻が入れる永代供養の期間のお墓を契約するか、妻が納骨されてから永代供養が開始する契約を選ぶと安心です。親子の場合ならさらに長い期間を想定しておく必要があります。永代供養料はその期間が短いと安く、長いと高いため、短い期間を選びがちですが、複数人で入りたい場合は注意が必要です。
永代供養のお墓には、「永代供養墓」「樹木葬」「納骨堂」があります。「永代供養墓」には、昔ながらの個人が建立するお墓もありますが、一般的には「合葬墓(がっそうぼ)」を指すケースがほとんどです。合葬墓は費用を最も抑えられますが、他の方の遺骨と一緒に納骨されるため、後から特定の故人の遺骨だけ返還してもらうことはできません。
「樹木葬」や「納骨堂」を選ぶ際は、一つの区画や納骨室の中に最大何柱(何人)分の遺骨が入るか確認しておくことが大切です。「最大8柱まで」とか、「3柱以上は追加料金が必要」など、墓地によって条件は異なり聞いてみないとわからないので、しっかり確認しておきましょう。
海や山などに遺骨を撒く「散骨」は、専門業者に遺骨をパウダー状にしてもらったのち、所定の場所で散骨します。それを全部撒いてもいいし、一部を撒いて残りを手元供養などにしてもよいのです。なお、条例で散骨が禁止されている場所があるため、個人で判断せず信頼できる業者を通じて撒くことをお勧めします。
「手元供養」にも様々な形があります。ミニ骨壺に納めたり、ダイヤモンドやパール、数珠など、様々な加工の仕方もあります。
どの方法にするにしても、供養する側が納得できることが大切です。すべてを散骨した家族の中には、「故人に手を合わせたくなったとき、どこに向かって手を合わせればいいかわからない」と、悔やむ人がいます。供養の対象がなくなる寂しさを感じるのです。そのため、散骨をする場合は一部の遺骨を手元供養として残すことも念頭に置いておくことをお勧めします。
手元供養の注意点としては、手元にあるその遺骨などを最終的にどうするのか、どのタイミングで最後の供養にするのかです。できるだけ長く受け継いでもらいたいと考えていても、将来、承継者が「知らない人の遺骨が手元にあるのは気持ちが悪い」と感じてしまうかもしれないからです。
供養の仕方は人それぞれ。どのような形であっても本人や供養する側の気持ちを考えたうえで決めることが大切です。
私たちが寺院や霊園などに持っているお墓の権利は、「永代使用権」という権利を購入している、という形です。祭祀承継者がいない場合、墓所を更地にして墓地管理者に返還する契約になっています。いわゆる「墓じまい」と呼ばれるものです。おひとりさまはもちろんのこと、親や先祖代々のお墓がすでにあるものの、自分たちは違うお墓に入るつもりなどで祭祀承継者がいないのなら、どのタイミングで墓じまいを実行するかも考えておかなければなりません。
墓じまいを検討する際、まずは親族にお墓の承継は可能かどうかを打診しましょう。お墓は相続財産ではないため、親族でも継ぐことができます。今あるお墓を親族に継いでもらうのが最も負担がない方法ですが、確認して誰も継ぐ人がいないとなれば、いよいよ墓じまいしかない、という流れになります。墓じまいの選択肢しかない、と納得してもらうためにも、親族に意向を聞いておくのは非常に大事なプロセスなのです。
墓じまいには、寺院や霊園などの墓地内に永代供養の墓があればそこに移すという方法もあります。同じ墓地管理者と石材店で完結できるため手続きも遺骨の移動もスムーズです。
最も負担が大きいのは、今の墓地ではない場所に遺骨を移転する方法です。この場合は改葬手続きが必要になります。改葬の手順は下図のとおりです。
| 手順 | 注意点 | |
|---|---|---|
| 1 | 家族や親戚に相談 | 親戚の理解や了解を得る |
| 2 | 墓地管理者に伝える | 墓じまいをしたい旨を伝える |
| 3 | 新しい墓の準備 | お墓を建立する場合は納骨日に合わせてお墓を建てる |
| 4 | 受入証明書を取得 | 新しい墓地管理者から発行してもらう |
| 5 | 改葬許可申請書を取得 | 今あるお墓の市区町村役場から入手する |
| 6 | 埋蔵(埋葬・収蔵)証明書を取得 | 今の墓地管理者から発行してもらう(改葬許可申請書に署名捺印をしてもらう場合もある) |
| 7 | 改葬許可証を取得 | 「受入証明書」「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」を今あるお墓の市区町村役場に提出し発行してもらう |
| 8 | 遺骨の取り出し | 閉眼供養(魂抜き)をしてもらった後、遺骨を取り出す。事前に寺院等とお墓の閉眼法要の日時を決め、遺骨の取り出しとお墓の解体工事を石材店に依頼しておく。法要費用は2万〜5万円程度。遺骨の取り出し費用は1柱当たり1万〜5万円程度 |
| 9 | 墓所の原状回復 | 石材店に墓所を更地にしてもらう。更地にする費用は墓区画の広さなどによっても異なるが30万〜100万円程度 |
| 10 | 新しいお墓へ納骨 | 新しいお墓の管理者へ改葬許可証を提出し、開眼供養(魂入れ)と納骨法要を行ってもらう。事前に寺院等と納骨法要の日時を決め、石材店に納骨の依頼をしておく |
墓じまいの際、皆さん気にされるのは離檀料です。離檀料の額を指定する寺院もありますが、特に決めていない寺院もあります。とはいえ、昔からお付き合いがある寺院の場合は、「今までお世話になり、ありがとうございました」の気持ちぐらいは形にして渡したほうがよいかもしれません。
時折、墓じまい後に「うちはもう墓参りに行かなくてよくなった」という声を聞くことがありますが、たとえ永代供養の墓に移したとしてもお墓参りには行ってください、とお伝えしています。
特に団塊の世代の方々は、家族に迷惑をかけたくないという意識が強いと感じています。そのためお墓に関しても永代供養墓や樹木葬、納骨堂、散骨を希望する人も珍しくありません。もちろん、そのお気持ちは尊いものであり、供養は故人のために行うものですが、残された人のためでもあります。
「あのとき、もっときちんと考えて供養していれば」、と後悔する人を多く見ていますが、手厚く供養して後悔する人には会ったことがありません。終活はその点を考えて進めてほしいと心から思います。
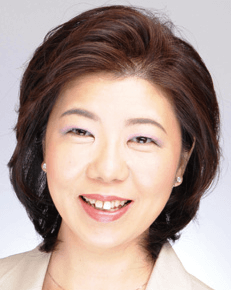
CFP®認定者、明石行政書士事務所/明石シニアコンサルティング 代表
明石 久美 氏
相続・終活コンサルタント、特定行政書士。千葉県松戸市を拠点におひとりさま準備、遺言書や民事信託契約書の作成、相続手続きなど相続業務を18年行っている。講師歴は20年、葬儀や墓などにも詳しく、相続・終活セミナーや研修を全国で行うほか、メディア出演、著書なども多数。
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP相談事例
2026.01.28
40代専業主婦。自営、無保険の夫が急死。長女を進学させられる?
FPトレンドウォッチ
2026.01.29
【速報版】2026年度税制改正大綱のポイントを解説!(上)
FP・専門家に聞く
2026.01.29
【税制改正】改正で注意したい2025年分の確定申告(備 順子氏)
FP・専門家に聞く
2026.02.02
分野/FP・エコノミストの一覧はこちらから!
FPトレンドウォッチ
2026.02.03
指数上昇で注目集まる J-REIT市場
FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)