CFP®試験1ワード解説
2026.02.02
暦年課税<相続・事業承継設計>
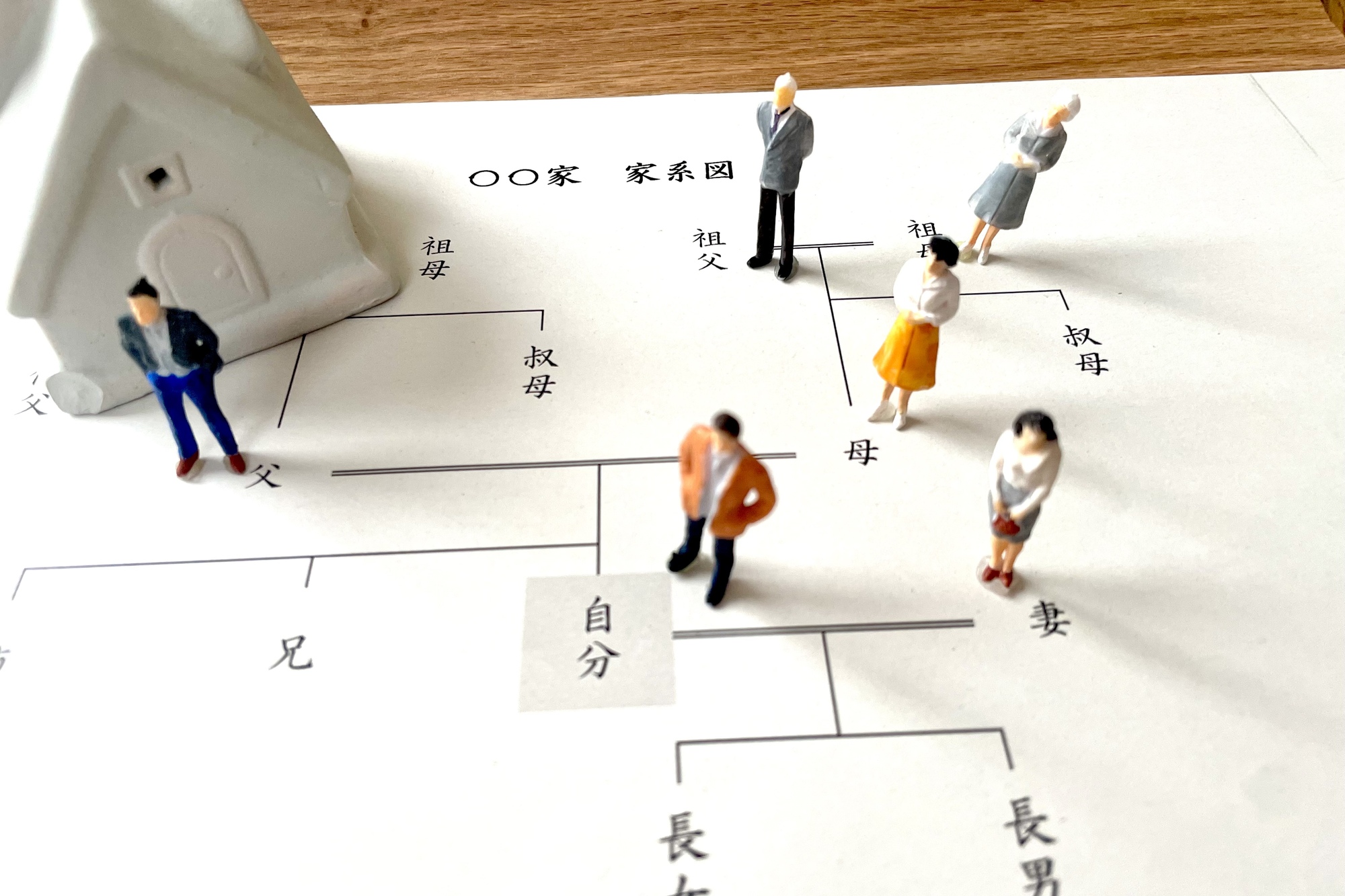
Share
公開:2025.10.01
更新:2025.10.10

CFP®資格審査試験の過去問題に登場した重要ワードをピックアップして解説します。
今月は「不動産運用設計」分野から、「抵当権と根抵当権」を取り上げます。
抵当権は、民法第369条で「債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と規定されています。
具体的には、住宅ローンなどの融資を受ける際に、金融機関(債権者)が借入者(債務者)の不動産を担保として設定し、債務者が返済できなくなった(債務不履行)になった場合に金融機関が担保の不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けることができるといったものです。
根抵当権は、民法第398条で特定の債権ではなく、あらかじめ定められた範囲内の不特定の債権について、設定された極度額(担保される債権の上限額)を限度に担保する抵当権と規定されています。
具体的には、事業資金の融資等において、極度額を一度設定(登記)しておけば、その範囲内であれば繰り返し借り入れが可能となります。
どちらも不動産を担保に融資を受ける際に設定される権利ですが、住宅ローン等のように一度限りの融資では抵当権が一般的です。ただし、次の図表に示したように、事業資金の融資等では根抵当権を設定するケースが考えられます。
| 特徴 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 債権の範囲 | 特定の債権のみを担保する | 極度額の範囲内で複数の債権を担保する |
| 権利の設定 | 登記が必要 | 登記が必要 |
| 権利の抹消 | 完済すると抹消登録ができるようになる | 完済しても債権者との合意が必要となる |
| 具体例 | 住宅ローンなど | 事業用の融資、リバースモーゲージなど |
解説:海宝 賢一郎氏(CFP®認定者)
本記事は執筆時点の情報に基づいており、最新の情報と異なる場合があります。
あわせて読みたい
この記事の閲覧は
日本FP協会会員限定です。
ログインすると下記の機能が利用できます。
24時間中にアクセスが多かった記事です。
1週間中にアクセスが多かった記事です
先週1週間中にいいね数が多かった記事です
1週間中にコメント数が多かった記事です
FP・専門家に聞く
2026.02.10
【経済動向】日本経済「失われた30年」は終わったのか?(永濱利廣氏)
FP・専門家に聞く
2026.02.03
【介護・施設】要介護者が入所できる 3つの公的な高齢者向け施設を知る(畠中雅子氏)
FPトレンドウォッチ
2026.02.12
日々の生活にも大打撃! 急増する「ランサムウェア」での被害
FPトレンドウォッチ
2026.02.09
新生活に向けてチェックしたい 引っ越しに関する手続きリスト(上)
FPトレンドウォッチ
2026.02.04
下取り?買い替え? 不要になったPC・スマホの処分方法
FPトレンドウォッチ
2025.09.03
いったん下がったコメ価格、実りの秋で再高騰?【トレンド+plus】